

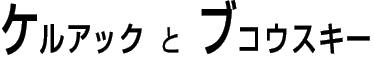 中上哲夫 『路上』や『孤独な旅人』『荒涼天使たち』の読者たちには<世界を放浪する作家>というイメージが強いと思うけど、ケルアックは同時に<ロウエルの作家>でもあった。 マサチューセッツ州ロウエルはケルアックが生まれ育った町で、ボストンの北西約50キロの工業都市。工業都市といっても、中心部を流れるメリマック川の水力発電を利用して繊維工業が発達したのは十九世紀の話。大恐慌以後繊維工業の中心は南部に移行し、ロウエルの繊維工業は衰退し、現在は皮革・電気機械・食料品などの諸産業が中心の、人口10万人(1990年)の地方都市だ。 この町に、ケルアックは1922年カナダ移民の子として生まれ、<リトル・カナダ>と呼ばれたフランス人地区で育った。ロウエルにはギリシア人地区やアイルランド人地区もあって、詩人のトーマス・フィッツシモンズに直接きいた話ではアイルランド系はフランス系と対立し、いつも喧嘩していたという(フィッツは、<息子>の意味で、アイルランドに多い姓。フィッツジェラルドも、そうだ)。 フランス語の世界で育ったケルアックは、小学校で初めて英語に出会って強い衝撃を受けた。その出来事は、かれの文学にまで深刻な影響を及ぼした。 ロウエルという町は、ケルアック本人が複数の作品で回想しているように、対立や差別、貧富の差の少ない、19世紀的調和をもった地方都市であった。ニューヨークやシカゴ、ロサンゼルスなどの大都市に顕著な緊張や対立、犯罪も、ロウエルまではほとんど及ばなかった。嘘のような話だけど、ほんとうだ。 この、活気のない穏やかな田舎町で、ケルアックは一級上のアイルランド系の鉄道員の娘と恋をしたり(『マギー・キャシディ』)、イタリア戦線で戦死したギリシア系のサンパスと文学を語り合ったり、ハイスクールのフットボールの花型選手になったりした(『ドゥルーズの虚栄』)。 ハイスクールを卒業すると、奨学金をもらってコロンビア大学へすすむべく故郷をあとにしてニューヨークへ向かったケルアックは、その後、人生の荒波にもまれることになった。そして、辛酸をなめるたびに思い出されるのが、ロウエルですごした幸福な日々であった。晩年、ロウエル出身の幼なじみの女性と結婚したのも、生まれ故郷ロウエルへの懐郷の表れだった。最後は、母親の健康を慮ってフロリダ州のピーターズバーグへ移住したけれども、その前に、いったんロウエルに引っ越したこともあった。終の栖として。 ケルアックは死んでロウエルのエディソン共同墓地に埋葬されたけれど、ロウエル以外にかれの埋葬地は考えられない。1979年、十周忌のミサのためにロウエルを訪れ、かれの墓前に立ったわたしは、その感をいっそう強くしたのだった。 理念としては人間はどこにでも住みうる存在であるけれども、実際はどこにでもすめるというわけではない。われわれが住む土地を選ぶというよりも、むしろわれわれは土地から選ばれるのではないのか。 コーソは、終生、育れたニューヨークを離れなかった。 スナイダーとマックルアは、ずっと生まれた土地--サンフランシスコとバークレー--に住んでいる。いまでも。 動いた詩人では、レックスロスはシカゴからサンフランシスコへ、ギンズバーグはニュージャージーからニューヨークへ、それぞれ移住したけれども、以後どこにも動かなかった。ニューヨーク生まれのファリンゲティも、サンフランシスコに移ってからはそこに居を構えているし。 こう見てくると、ロウエル→ニューヨーク→バークレー→ニューヨーク→ロウエル→フロリダと移り住んだケルアックの生涯は、異様な印象を与えるのだ。ケルアックは、どうしてそんなにあちこちてんてんと移り住んだのだろうか。フランス系カナダ人の家系に生まれ育ったジャック・ケルアックは、ついに住むべき場所を見つけられなかったのだ。 ロウエルこそ、住むべき場所だ、とケルアックは何度も思ったであろう。晩年、ロウエルに移り住んだのはそのためだったと思う。しかし、現実のロウエルはかれの想念のなかのロウエルとは微妙にずれていた。夜ごと夜ごと、ロウエルの酒場から酒場を飲み歩いても、かれのロウエルはどこにもなかったのだ。 ケルアックの最大の悲劇は、アメリカ人としてのアイデンティティを確立できなかったことにあったと思う。それを端的に表わしているのが、衝動的ともいえる度重なる転居だった。ロウエルを舞台に数々の作品を書いたのも、アイデンティティを定めようとする必死の営為だったのだという気がする。ロウエルこそ、ケルアックにとって最後の砦だったのだ、と。とすると、ジャック・ケルアックは<ビート作家>というよりも<ロウエルの作家>だったといった方がかれの実体に近いのではないか。最近のわたしはそんな気が強くして仕方ないのだけど。(2002・10・13) *筆者(なかがみ・てつお)は詩人、翻訳者。 |